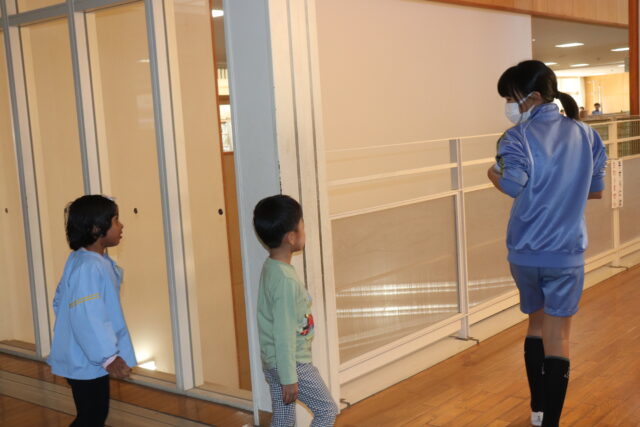12月2日(火)、5年生が校外学習に行きました。
富山きときと空港では、展望デッキや空港の施設を見学しました。


続いて訪れたBBT放送局では、スタジオやニュースづくりの現場を間近で見学しました。実際の機材を見たり、ニュース番組作りの裏側について説明を聞いたりして、番組作りに関わる人たちの仕事やその人たちの工夫や努力について知りました。


富山市科学博物館では、プラネタリウムを鑑賞しました。ゆったりとしたドームの中で、季節の星座や宇宙のひみつについて映像とともに学ぶことができました。館内見学では様々な実験装置を試して楽しみ、「もっとみたかった!」という声も聞かれました。


一日を通して、子供たちは新しい発見や感動をたくさん味わうことができました。